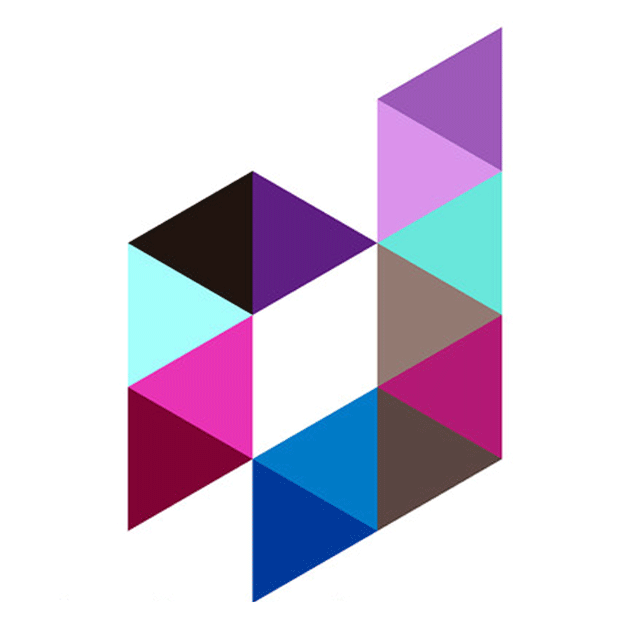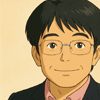【相続税対策】農地等の納税猶予の特例とは?~農地を守りつつ納税を猶予する制度~
目次
はじめに
相続税の申告において、農地を相続した場合に大きな税負担が発生することがあります。しかし、一定の要件を満たせば「農地等の納税猶予の特例」を活用して、相続税の納税を猶予することができます。
この記事では、税理士の視点から、この特例の概要と適用要件、注意点についてわかりやすく解説します。
農地等の納税猶予の特例とは?
農地等の納税猶予の特例とは、被相続人が農業を営んでいた農地を相続し、相続人が引き続き農業を継続する場合に、その農地に係る相続税の納税を猶予できる制度です。
将来的に一定の条件を満たせば、猶予された相続税が免除される可能性もあります。
この特例が必要とされる理由
農地の評価額は高額になることが多く、相続税の負担が大きくなります。しかし、現金で納税することが困難な農家も多く、納税のために農地を売却する事態が生じかねません。
この制度は、農地の保全と農業の継続を目的に設けられているのです。
納税猶予の対象となる農地の種類
- 特定農地(生産緑地、農地法の許可が必要な農地)
- 貸付け農地(相続直前に賃貸借契約していた場合など、要件を満たせば対象)
納税猶予の主な要件
1. 被相続人に関する要件
- 相続開始時点で農業を営んでいたこと
- 対象農地を自ら耕作していたこと
2. 相続人に関する要件
- 相続税の申告期限までに、農業を開始していること
- 対象農地を耕作する意思と能力があること
- 納税猶予の特例の適用を申告書で選択すること
- 「農業委員会等の証明書」を取得していること
3. 継続要件
- 原則として20年間(相続時から)農業を継続することが求められます(死亡時などの例外あり)
納税猶予の効果
- 対象農地にかかる相続税の全額または一部が猶予される
- 継続要件を満たせば、猶予税額は最終的に免除される
途中で農業をやめたらどうなる?
以下のような場合には、猶予されていた相続税と利子税が一括で課税されます。
- 農業を廃業した
- 対象農地を売却した
- 耕作を他人に委託した(一定の場合を除く)
必ず専門家に相談を
この特例は非常に有利ですが、要件が細かく、申告や証明書の取得など専門的な手続きが必要です。
失敗すれば逆に多額の税金が発生するリスクもあるため、必ず税理士などの専門家にご相談ください。
まとめ
農地等の納税猶予の特例は、農地を守り、農業を継続するためにとても重要な制度です。
要件を正しく理解し、計画的に対策することが、農家の相続においては不可欠です。
当事務所では、農地の相続や納税猶予の申請支援を多数行っております。
ご相談はお気軽にどうぞ。