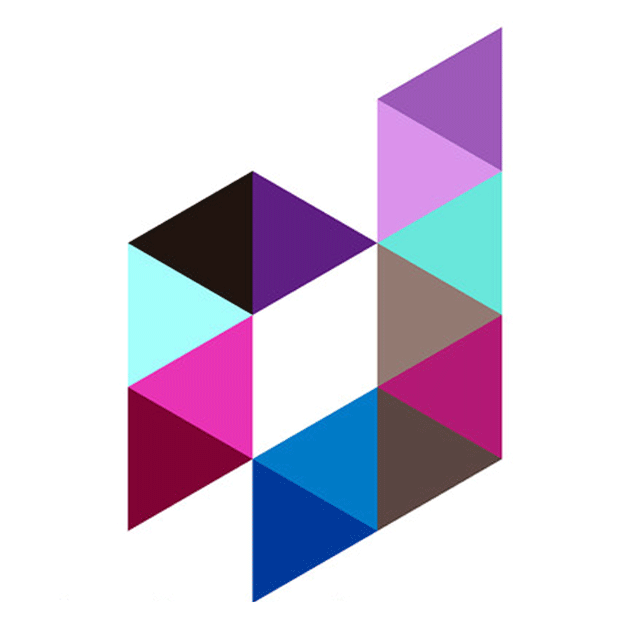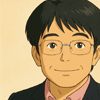【相続税対策】親の土地に小規模宅地等の特例を使うには?適用のための4つの条件を解説
相続税の申告において、「小規模宅地等の特例」は非常に強力な節税手段です。特に親から相続した自宅の土地にこの特例が適用できれば、最大で330㎡まで土地の評価額が80%減額されます。
今回は、小規模宅地等の特例が使えるための具体的な要件について、税理士の視点からわかりやすく解説します。
小規模宅地等の特例とは?
相続や遺贈によって取得した宅地のうち、一定の要件を満たす場合に、その土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
対象となる土地の種類は大きく分けて以下の3つです:
- 特定居住用宅地(自宅)
- 特定事業用宅地
- 貸付事業用宅地
本記事では最も相談が多い「特定居住用宅地(親の自宅)」に絞って解説します。
小規模宅地の特例が親の自宅に適用される4つの条件
① 被相続人が死亡時点でその宅地に住んでいたこと
まず大前提として、被相続人(親)が亡くなる直前までその自宅に住んでいた必要があります。
老人ホームに入所していた場合でも、一定の条件を満たせば適用可能です(※詳しくは後述)。
② 相続人が「親族」であり、かつ一定の条件を満たすこと
土地を相続した人(= 相続人)が、以下のいずれかに該当する必要があります:
・配偶者
無条件でOKです。配偶者が土地を相続すれば、必ず特例が適用されます。
・同居親族(同居していた子など)
以下を満たすことが条件です。
- 相続開始時に被相続人と同居していたこと
- 相続税の申告期限までその土地に住み続けていること
・別居親族(主に子)
別居していた場合はハードルが上がります。
以下の条件すべてを満たす必要があります。
- 被相続人に配偶者も同居親族もいない
- 相続開始時に持ち家に住んでいない(=賃貸など)
- 相続税の申告期限までその宅地を売却・貸出していない
③ 相続税の申告をしていること
この特例は申告しなければ適用されません。
つまり、相続税の申告が必要ない場合でも、特例を適用したいなら申告書を提出する必要があります。
④ 土地の面積が特例の限度内であること
- 特定居住用宅地の限度面積は330㎡(100坪)
- 330㎡を超える部分は通常通りの評価額となります
たとえば、500㎡の土地を相続した場合、330㎡までは80%減額、それを超える170㎡はそのまま評価されます。
【ケース別】特例が使える?使えない?判断のポイント
✔ 同居していた子が相続 → 使える(申告期限まで住み続ければ)
✔ 別居の子が相続 → 条件に注意(持ち家があると原則NG)
✔ 老人ホーム入所中に死亡 → 「やむを得ない事情」であればOK
【まとめ】適用の可否は事前の確認が必須です
小規模宅地等の特例は、要件を一つでも満たさなければ使えません。
とくに「同居の有無」や「持ち家の有無」が分かれ目となります。
親の土地を相続する可能性がある方は、早めに税理士に相談し、生前の対策と申告時の対応をセットで考えることが大切です。
✅ 無料相談受付中【舩橋信治税理士事務所】
当事務所では相続税に強い税理士が、小規模宅地等の特例を最大限活用した申告・生前対策をサポートしています。
まずはお気軽にご相談ください。