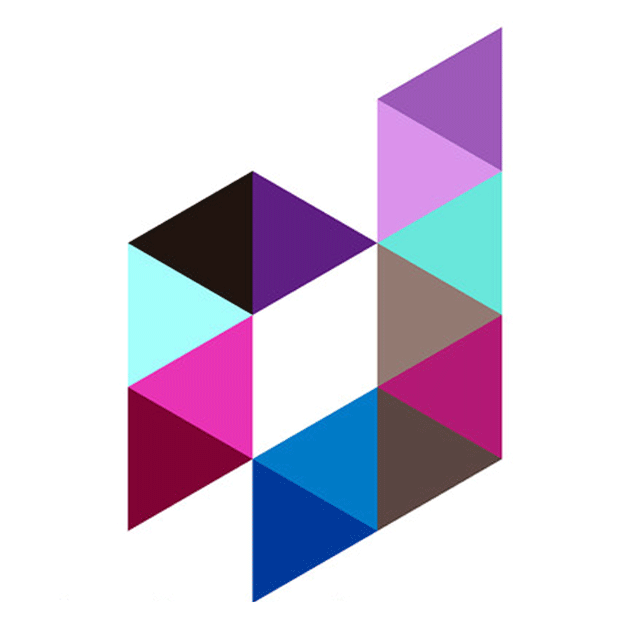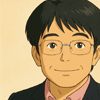【相続税対策】保険金の非課税制度とは?うまく活用すれば相続税が軽減できます
執筆:税理士 舩橋
相続税の申告において、保険金には一定の「非課税枠」があることをご存じでしょうか?
この制度をうまく活用することで、相続税を合法的に軽減することが可能です。
この記事では、相続税における生命保険金の非課税制度について、税理士の立場からわかりやすく解説いたします。
■ 生命保険金は相続財産になるの?
まず前提として、被相続人(亡くなった方)が契約者かつ被保険者となっていた生命保険契約で、死亡保険金を受け取った場合、その保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
ただし、ここで重要なのが「非課税枠」の存在です。
■ 非課税になる金額の計算方法
生命保険金については、次の計算式により一定金額まで非課税になります。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が3人いる場合は、
500万円 × 3人 = 1,500万円までが非課税になります。
この金額以下の保険金であれば、相続税は課税されません。これを「生命保険金の非課税枠」といいます。
■ 注意点:非課税枠を受けられる条件
非課税制度を使うには、以下のポイントを満たしている必要があります。
- 被保険者=被相続人であること
- 保険金の受取人が相続人であること
- 相続税の申告対象であること(基礎控除以下でも申告が必要な場合あり)
また、遺言によって受取人が指定されている場合などは、制度の適用可否に注意が必要です。
■ 非課税制度をうまく使うポイント
生命保険は、現金で受け取れる財産であるため、相続後の納税資金にも充てやすいというメリットがあります。
また、生命保険金の非課税枠は、預金などの他の財産には適用されないため、現金のまま残しておくよりも、保険に形を変えておくことで節税につながります。
■ 税理士からのひとこと
生命保険を利用した相続税対策は、比較的簡単かつ確実性の高い方法です。しかし、制度の適用条件や、他の相続財産との関係を踏まえた総合的なプランニングが重要になります。
「この契約は非課税の対象になるの?」「相続人ごとの受取額はどうするべきか?」といったご相談にも対応しておりますので、気になる方はお気軽に当事務所までご相談ください。
■ まとめ
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 非課税の対象 | 被相続人が契約者・被保険者、かつ相続人が受取人の死亡保険金 |
| 非課税限度額 | 500万円 × 法定相続人の数 |
| メリット | 相続税の節税・納税資金の確保にも有効 |
生命保険の活用は、相続税対策の“基本”ともいえる手法です。
制度を正しく理解し、適切に活用することで、将来の相続に備えることができます。