小規模宅地等の特例とは?相続税を大きく節税できる制度の条件を解説
親から土地を相続したとき、相続税が思いのほか高くて驚かれる方が少なくありません。特に、自宅の敷地や事業用の土地は評価額が高くなりがちです。しかし、相続税の計算において 「小規模宅地等の特例」 を適用できれば、大幅な節税が可能になります。
今回は、この特例の概要と適用の条件を、相続専門の税理士の視点からわかりやすく解説します。
小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、一定の条件を満たす場合に、被相続人(亡くなった方)の土地の評価額を 最大80%まで減額 できる制度です。
この制度の目的は、「相続によって住む場所や事業の基盤を失わないようにすること」。したがって、 居住用や事業用の土地 が対象となります。
小規模宅地の特例が使える主な土地の種類
小規模宅地等の特例は、大きく分けて以下の3種類の宅地に適用されます。
1. 居住用宅地(特定居住用宅地等)
被相続人が 自宅として使用していた土地 で、相続人が一定の要件を満たしている場合に適用されます。
- 減額率:土地330㎡まで80%評価減
2. 事業用宅地(特定事業用宅地等)
被相続人が 自営業や法人事業のために使用していた土地。
- 減額率:土地400㎡まで80%評価減
3. 貸付事業用宅地(貸付事業用宅地等)
被相続人が アパートや駐車場などを貸していた土地。
- 減額率:土地200㎡まで50%評価減
居住用宅地における特例の適用要件
ここでは、特に相談の多い 居住用宅地 に絞って、特例を適用できるケースと条件を詳しく見ていきます。
適用対象者(相続人)の要件
被相続人の自宅を相続した方のうち、次のいずれかに該当すれば、特例を受けられる可能性があります。
【1】配偶者
配偶者は 無条件で適用可能。住んでいなくてもOKです。
【2】同居していた親族
被相続人と同じ家に住んでいた子などは、 そのまま引き続き居住を継続することが条件 です。
【3】別居の親族(いわゆる「家なき子」)
別居していても、自分名義の家を持っていない子などは適用可能な場合があります。
※ただし、過去3年以内に持ち家を所有していた場合などは適用不可。
適用のための注意点
- 相続税の申告が必要:たとえ相続税がゼロになっても、申告しないと特例が受けられません。
- 居住の継続:同居相続人は、 申告期限まで住み続けている必要 があります。
- 賃貸や売却をするとNGになることも:特例の前提が崩れると適用が取り消される可能性があるため注意が必要です。
まとめ|専門家に相談して確実な節税を
小規模宅地等の特例は、適用できれば 数百万円〜数千万円単位で相続税が軽減 される非常に有効な制度です。しかし、要件が細かく、誤解しやすいポイントも多いため、申告には注意が必要です。
「自宅を相続したけど、特例が使えるかわからない」
「家なき子として申告したいけど、条件を満たしているか不安」
このような方は、相続税の実務に詳しい税理士に早めにご相談されることをおすすめします。
※本記事は、2025年7月現在の税法に基づいて執筆しています。制度の変更がある場合もありますので、最新の情報をご確認ください。
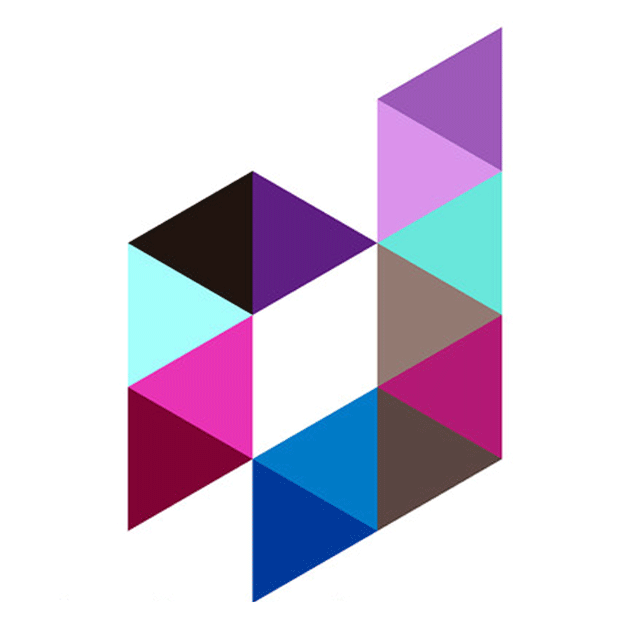

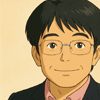
コメント